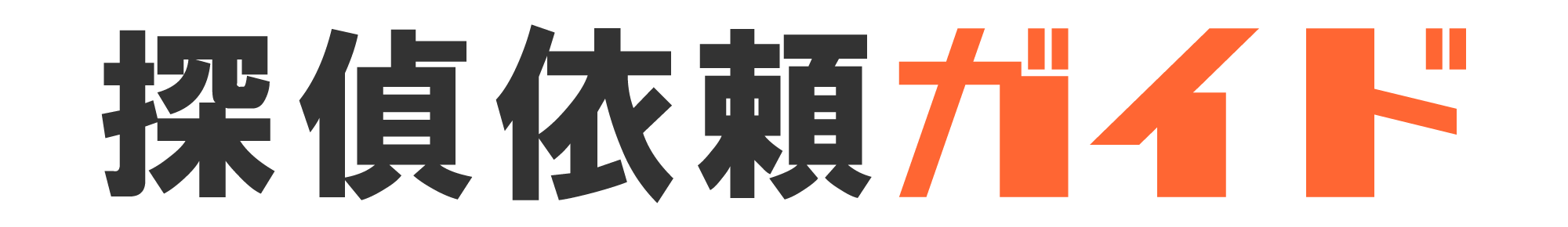探偵事務所と専属契約(専任契約、一社専属など)を締結すれば、他社への調査依頼ができない代わりに優先的対応を受けるなどのメリットが期待できます。しかし、契約書の内容が不明瞭であったり、料金体系が複雑だったりすると、追加費用や成果不一致、途中解約時のトラブルにつながるリスクも存在します。本記事では、専属契約を結ぶ際に確認すべき契約条項、注意すべき料金制度、解約・中断ルール、証拠の扱い、トラブル回避策を解説します。安心して専属契約を行うための判断基準を提供します。
- 契約期間・専属の範囲(他社依頼禁止の有無)を確認しているか
- 成果の定義・達成条件を明確に契約書に記載してもらっているか
- 料金構成(基本料・成功報酬・追加経費など)が詳細に説明されているか
- 解約・中断規定(違約金・返金条件など)を確認しているか
- 契約書・重要事項説明書・誓約書がきちんと交付されているか
専属契約の背景にある依頼者のニーズと実態
専属契約を選ぶ依頼者ニーズの増加
近年、探偵事務所との専属契約を希望する依頼者が増加しています。特に浮気調査や企業内調査など、機密性や継続性が求められる案件では、同じ探偵に一貫して対応してもらえるという安心感から、専属契約が注目されています。こうした契約では、他の探偵事務所への依頼が制限される一方、継続的な調査の実施、柔軟な対応、調査対象の変化にも即応できる体制が整えられることが多いのが特徴です。調査の背景や目的が複雑で、長期的な関与が必要とされるケースでは、専任契約が理にかなっていると感じる依頼者が増えている傾向にあります。
専属契約の利点と注意点
専属契約には、特定の探偵事務所と強固な関係を築くことで得られるメリットがあります。たとえば、調査計画の柔軟な変更、優先的な調査対応、担当者の継続による情報共有の効率化などが挙げられます。しかし一方で、契約内容をしっかり確認せずに専属契約を結んでしまうと、「思ったほど調査が進まない」「成果が得られない」「解約できない」などのトラブルにつながるリスクもあります。また、他社と比較検討する機会を失い、より適切な調査プランを見逃す可能性もあるため、専属契約を結ぶ際は慎重な検討が求められます。
専属契約のリスクと留意点
- 解約制限のリスク|途中で調査方針を変更できない契約構造
- 成果保証の不在|専属でも調査結果が保証されない場合がある
- 他社比較の機会損失|より条件の良い事務所を検討できなくなる
- 担当固定による依存性|相性が合わない場合の変更が難しい
- 契約内容の不透明性|説明不足のまま同意すると後悔の原因に
専属契約の拡大と法的観点
専属契約の拡大に伴い、契約の透明性と法的適正性も注目されています。依頼者保護の観点からは、「契約書の明示」「報告頻度の明記」「解約条項の明文化」などが重要視されており、特に消費者契約法や特定商取引法の観点からも契約内容が適切であることが求められます。探偵業法上も、重要事項の説明義務や個人情報の取り扱いに対して明確なルールがあり、専属契約においてもそれに準じた運用が必要です。探偵にとっても、信頼関係の維持と契約トラブルの未然防止のために、丁寧で誠実な説明が不可欠となっています。
専属契約を結ぶ前に確認すべき契約書のチェックポイント
契約範囲と専属条件の明確化
専属契約を結ぶ際に最初に確認すべきは、専属の範囲とその拘束内容です。「依頼者が他の探偵事務所に並行して依頼を行うことを禁止する」という条項がある場合、それに違反すれば契約解除や違約金が発生する可能性があります。また、契約書に「契約期間中は他社への相談・依頼を行わないこと」と記載されているかどうかを必ずチェックし、拘束の範囲を明確にしておきましょう。
成果の定義と報酬発生条件の確認
専属契約における調査成果とは何か、そしてどの時点で報酬が発生するのかも重要な確認ポイントです。たとえば「浮気相手との接触写真1回で成功と見なす」のか、「複数回の証拠取得が必要」なのか、曖昧な定義のまま契約すると、期待と現実のズレが生じてトラブルの原因になります。また、成功報酬が「証拠取得の有無」なのか「裁判での有効性」なのかも確認しておく必要があります。
成果の定義と報酬発生条件
- 成果の定義曖昧|何をもって「成功」とするか明確でない契約
- 報酬の発生条件不明|いつ費用が発生するかの基準が曖昧
- 証拠の質の不一致|期待する証拠レベルと契約内容が合致しない
- 成果未達でも費用請求|証拠不十分でも費用が発生する可能性
- 成功報酬の条件錯誤|「裁判有効性」か「接触確認」かの定義が不明
契約期間と更新・延長の取り扱い
専属契約の多くは1ヶ月〜6ヶ月などの一定期間に設定されており、その後の更新や延長についても事前に説明が必要です。自動更新の有無、延長時の費用変動、契約満了後の再契約条件など、継続を前提とした仕組みについて明確にしておくことが重要です。万が一、契約期間終了後に追加調査が必要となった場合の取り扱いも確認しておくと安心です。
専属契約での料金トラブルを防ぐための知識
基本報酬と成功報酬の構成を把握する
専属契約では、基本料金と成功報酬が別々に設定されていることが一般的です。基本料金には調査計画の立案、下見、準備費などが含まれ、成功報酬は証拠の取得や目的の達成に応じて発生します。ただし、「どのタイミングで」「何に対して」成功報酬が発生するかが不明確な場合、依頼者との間でトラブルになるケースがあります。調査の成果が得られなかったにもかかわらず成功報酬が発生してしまうような契約内容であれば、契約前に再確認が必要です。
追加費用の種類と発生条件を確認
料金体系で注意すべきなのは、調査以外にかかる追加費用の存在です。主な追加費用には、交通費、宿泊費、機材費(特殊カメラやGPSなど)、報告書作成費、調査員の増員費用などがあります。これらが「別途発生」となっているのか、「基本料金に含まれている」のかは事務所によって異なり、契約前に説明を受けていなければ、後から高額な追加費用を請求される可能性もあります。
時間超過・日数延長のコストも把握
専属契約の場合、契約時間や日数を超えて調査が必要となることも珍しくありません。その際に「延長1時間ごとに〇〇円」や「日数延長1日ごとに追加料金」といった条項が設定されていることがあります。依頼者としては、こうした延長費用の有無とその計算方法を事前に把握しておくことが大切です。場合によっては、契約時に「上限費用(キャップ)」を設定してもらうことも一つの防衛策となります。
契約解除・中断時の条件と依頼者が守るべき注意点
中途解約と違約金規定を契約前に確認
専属契約を締結する際に最も注意すべきポイントの一つが、中途解約に関する規定です。契約期間中であっても、調査の必要性がなくなったり、依頼者の事情で調査を中止したい場合が発生する可能性があります。その際、契約書に「中途解約不可」や「違約金が発生する」などの条項があると、高額な支払いを求められることになります。特に、契約内容が抽象的な場合や、口頭での説明だけで契約してしまった場合には、依頼者が不利な条件に気づかずトラブルになることもあります。こうしたリスクを避けるためには、契約書に明記されている解約条項を事前に確認し、不明な点は無料相談の段階で具体的に質問しておくことが重要です。
調査中断と費用の扱いに要注意
調査期間中に対象者の行動が変化したり、依頼者の都合で一時的に調査を停止せざるを得ないケースもあります。こうした「調査中断」が発生した場合、その期間の費用がどう扱われるかは契約内容によって異なります。たとえば、調査が一時停止中でも日割りで費用が発生する契約や、再開時に再契約が必要な形式も存在します。調査中断時の取り扱いが不明確なままだと、依頼者にとって大きな不利益につながるため、契約前に「中断可能か」「その間の費用はどうなるか」「再開はスムーズか」などの確認が欠かせません。また、緊急事態に備えて中断や延期の条件を契約に盛り込むことも、トラブル予防に効果的です。
契約期間終了後の対応と権利関係も確認
契約期間が満了した後に、追加の調査を希望する場合や、取得した証拠を活用する必要が出てくることもあります。その際、調査報告書や証拠データの権利が誰に帰属するか、再契約が必要か、報告書の再発行や追加報告の対応が可能かといった点も事前に確認しておくべきです。また、契約終了時点で未使用の調査日数が残っていた場合、それが繰り越し可能か、または返金対象となるかといった条件も、事務所ごとに扱いが異なります。調査後のサポート体制やアフターフォローの有無によって、依頼後の満足度は大きく変わります。専属契約だからこそ、契約終了後まで見据えた内容設計が求められます。
調査結果の取り扱いと依頼者の権利を明確に
調査報告書の形式と提出方法
専属契約では、調査結果の提出方法やその内容も契約によって定められています。一般的には、調査報告書として紙媒体またはPDF形式で提出され、日時・場所・対象者の行動が写真や文章で記録されますが、その内容の詳細さや見やすさは事務所によって異なります。また、動画や音声などのデジタルデータをUSBやDVDで受け取れるかどうかも確認しておきたいポイントです。報告書の提出タイミングや、途中経過の速報の有無、修正依頼への対応可否なども契約時に明示しておくことで、調査終了後の混乱を防げます。
証拠の保管・再発行・使用範囲の明確化
証拠資料の取り扱いは、報告後にも重要な意味を持ちます。提出された写真や映像、書面は、一定期間は探偵事務所が保管する場合もありますが、個人情報や機密性が高いため、依頼者が保管責任を持つ形で返却されることが一般的です。また、報告書の再発行が可能か、再利用にあたっての制限があるかも重要な確認事項です。法的手続きに証拠を使う際には、調査日時や事実の正確性が問われるため、原本の状態や記録の信頼性も確保されている必要があります。契約時に「証拠の取扱条件」について書面で取り決めておくと安心です。
守秘義務・第三者提供の制限と依頼者の権利
専属契約の最大のポイントの一つが「情報の独占性」と「守秘義務の徹底」です。探偵事務所は、調査によって得た情報を第三者へ漏らすことは許されず、契約終了後も守秘義務を継続するのが原則です。ただし、依頼者が他の事務所に資料提供を希望する場合、それが契約上禁止されていないかも確認が必要です。逆に、探偵側が調査資料を今後の営業資料に転用したり、社内教育目的に使うことがないよう、資料利用範囲を限定する条項を契約に盛り込むことも有効です。依頼者のプライバシー保護と証拠の利用権については、双方の合意のもとで明文化しておくことが信頼関係の維持につながります。
専属契約で成功した事例・失敗した事例から学ぶ
専属契約で報告体制に満足できた事例
30代の女性が、夫の不倫調査で探偵事務所と専属契約を締結。契約前の無料相談で、専任担当者の継続対応・中間報告の頻度・報告書の具体的な構成まで細かく確認したうえで契約に踏み切った。実際の調査では、週1回の進捗報告があり、対象者の行動変化にも柔軟に対応。証拠は時系列で整理され、法的にも有効な内容であったため、慰謝料請求にも大きく貢献した。依頼者は「専属契約だからこそ、最初から最後まで安心して任せられた」と高評価をしている。
契約内容を曖昧にした結果トラブルに発展した事例
40代男性が、企業内部の横領疑惑に対して探偵と専属契約を結んだが、契約書の内容をよく確認しないまま署名。報告書の提出時期が曖昧だったため、3週間以上報告がないまま調査が継続。加えて、成果が出なかったにもかかわらず高額な成功報酬が請求された。交渉の末、違約金を支払って契約を途中解約することに。後日、別の探偵事務所に依頼し直すことになった。依頼者は「契約の細かい条項を確認していなかったことが最大の失敗だった」と語る。
契約解除後の証拠再利用で揉めた事例
50代女性が、かつての不倫調査で得た証拠を別の事務所に再調査の参考として提供しようとしたところ、前契約の探偵事務所から「証拠は第三者提供禁止」と指摘されトラブルに発展。契約書にその条項が記載されていたものの、当初の説明が不十分で、依頼者はその制限を認識していなかった。証拠の再利用に関する明確な合意がなかったことから、双方の認識にズレが生じた事例であり、契約書の読み込みと説明責任の重要性を示すケースとなった。
よくある質問(FAQ)
専属契約を結ぶと他の探偵事務所に依頼できなくなりますか?
はい。基本的に専属契約には「他社への調査依頼を禁止する」条項が含まれる場合があります。契約の範囲内でのみ調査を実施し、情報漏洩や重複調査のリスクを避けることを目的としています。ただし、契約書に記載がない場合や例外条項がある場合もあるため、契約時に明確にしておくことが重要です。
専属契約で失敗しないために最も大切なことは?
契約前に、内容を細部まで確認し、口頭説明と契約書の記載にズレがないかをチェックすることが最も重要です。特に、報告頻度、成功報酬の条件、解約時の対応、証拠の扱いなど、後からトラブルになりやすい部分については、書面で明文化されているかを必ず確認しましょう。また、初回の無料相談で遠慮せず質問を重ねることが、納得感のある契約につながります。
契約後に条件を変更することは可能ですか?
基本的には、契約内容の変更には双方の合意が必要です。依頼者側の事情で調査期間を延長したり、報告書の形式を変更する場合など、途中で契約内容を調整することは不可能ではありませんが、必ず事前に連絡し、書面で取り決めを交わすことが原則です。口頭での合意だけで進めてしまうと、トラブルの原因になるため注意が必要です。
専属契約は信頼関係と契約内容の明確化が鍵
探偵事務所との専属契約は、継続的かつ機密性の高い調査において非常に有効な手段です。しかしその反面、契約内容や料金体系が不明瞭なまま締結してしまうと、途中での解約や費用面、報告内容などをめぐってトラブルになる可能性も否定できません。特に成果報酬の定義、中間報告の頻度、証拠の取扱いと使用範囲、そして解約条件などについては、契約書で明文化されたうえで合意することが不可欠です。専属契約は、信頼できる探偵事務所と丁寧な事前相談を重ねることで、そのメリットを最大限に活かすことができます。最終的に後悔のない調査結果を得るためには、「契約前に何を確認し、どんな条件で合意したか」がすべての土台になります。まずは無料相談を利用し、疑問点を一つずつ解消してから契約に進みましょう。
※当サイトでご紹介している相談内容はすべて、探偵業法第十条に準じて、個人情報の保護に十分配慮し、一部内容を変更・修正のうえ掲載しています。探偵ガイドは、初めて探偵を利用する方に向けて、安心・納得して依頼できるよう、調査の基礎知識や依頼時の注意点、探偵選びのポイントをわかりやすく解説する情報提供サイトです。
週刊文春に掲載 2025年6月5日号
探偵法人調査士会が運営する「シニアケア探偵」が週刊文春に掲載されました。一人暮らしの高齢者が増加している背景より、高齢者の見守りツールやサービスは注目されています。シニアケア探偵も探偵調査だからこそ行える見守り調査サービスを紹介していただいています。昨今、日本の高齢者問題はますます深刻さを増しています。少子高齢化の進行により、多くのご家庭が介護や見守りの悩み、相続の不安、悪質な詐欺や被害などの金銭トラブルに直面しています。「シニアケア探偵」の高齢者問題サポートは、こうした問題に立ち向かい、高齢者の皆様とご家族をサポートするために設立されました。

この記事の作成者
探偵調査員:北野
この記事は、はじめて探偵を利用される方や困りごとを解決するために探偵利用を考えている方に向けて、探偵の使い方をできるだけ分かりやすく知っていただくために調査員の目線で作成しました。探偵利用時に困っていることや、不安に感じていることがあれば、当相談室へお気軽にご相談ください。どんな小さなことでも、お力になれれば幸いです。

この記事の監修者
XP法律事務所:今井弁護士
この記事の内容は、法的な観点からも十分に考慮し、適切なアドバイスを提供できるよう監修しております。特に初めて探偵を利用される方は、有益な利用ができるようにしっかりと情報を確認しましょう。法的に守られるべき権利を持つ皆様が、安心して生活できるよう、法の専門家としてサポートいたします。

この記事の監修者
心理カウンセラー:大久保
人生の中で探偵を利用することは数回もないかと思います。そのため、探偵をいざ利用しようにも分からないことだらけで不安に感じる方も多いでしょう。また、探偵調査によって事実が発覚しても、それだけでは心の問題を解決できないこともあります。カウンセラーの立場から少しでも皆様の心の負担を軽くし、前向きな気持ちで生活を送っていただけるように、内容を監修しました。あなたの気持ちを理解し、寄り添うことを大切にしています。困ったことがあれば、どうか一人で悩まず、私たちにご相談ください。心のケアも、私たちの大切な役割です。
24時間365日ご相談受付中

探偵依頼に関する相談は、24時間いつでもご利用頂けます。はじめてサービスを利用される方、依頼料に不安がある方、依頼を受けてもらえるのか疑問がある方、まずはご相談ください。専門家があなたに合った問題解決方法をお教えします。
探偵依頼に関するご相談、探偵ガイドに関するご質問は24時間いつでも専門家がお応えしております。(全国対応)
探偵依頼に関するご相談はLINEからも受け付けております。メールや電話では聞きづらいこともLINEでお気軽にお問合せいただけます。質問やご相談は内容を確認後、担当者が返答いたします。
探偵依頼に関する詳しいご相談は、ウェブ内各所に設置された無料相談メールフォームをご利用ください。24時間無料で利用でき、費用見積りにも対応しております。
探偵法人調査士会公式LINE
探偵法人調査士会では、LINEからの無料相談も可能です。お仕事の関係や電話の時間がとれない場合など、24時間いつでも相談可能で利便性も高くご利用いただけます。