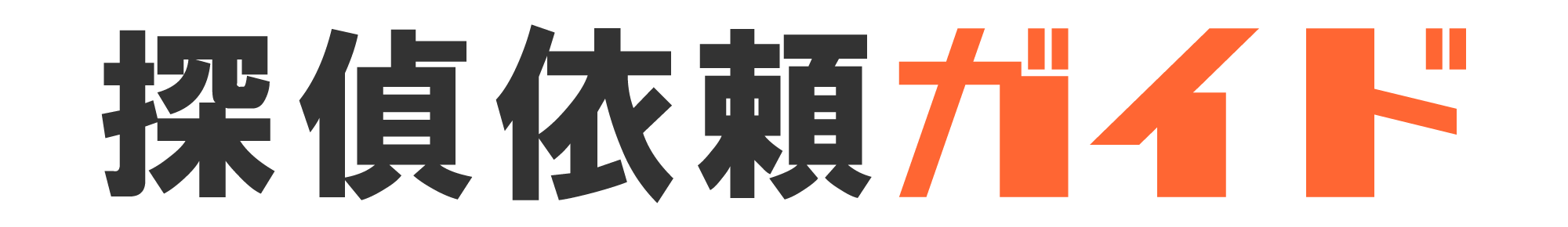近年、多くの企業が「従業員の定着率の低さ」や「人材流出」に課題を抱えています。その背景には、表向きには語られない「本当の退職理由」が隠されていることも少なくありません。退職者に対する第三者機関によるリサーチを活用すれば、忖度のないリアルな声を収集でき、社内体制や人間関係、評価制度、働き方などの問題点を明確化できます。本記事では、退職者リサーチのメリット、調査手法、結果の活用方法などを詳しく紹介し、離職防止・社内改革に活かす実践的な手法を解説します。
- 従業員の退職理由がいつも「一身上の都合」で曖昧
- 特定の部署で退職者が集中している
- 面談では本音が出てこないと感じている
- 離職率が高く、採用コストが膨らんでいる
- 客観的な視点で社内課題を把握したい
「辞めた理由」を見過ごすことがもたらすリスク
退職者が語らない「本当の理由」とは
企業が把握している退職理由の多くは、「一身上の都合」や「キャリアアップ」など表面的なものにとどまりがちです。しかし実際には、上司との人間関係、職場の風土、過剰な業務負担、評価制度への不満など、言いづらい本音が存在しています。これらの問題は、本人が在職中に口に出しにくいだけでなく、退職時の面談でも遠慮や忖度から明かされないことが少なくありません。こうした「本当の理由」を正確に把握しないままでは、社内環境の根本的な課題は放置され、同様の離職が繰り返される恐れがあります。
高い離職率が企業にもたらすダメージ
従業員の離職が続くと、採用コストや教育コストの増加、業務の属人化による生産性低下など、企業経営にさまざまな悪影響を及ぼします。また、残された社員に業務負担が集中すれば、モチベーションや定着意欲の低下にもつながり、組織全体のパフォーマンスが下がる要因となります。さらに、求人市場での評判や「辞めやすい会社」といったレッテルが付くことで、優秀な人材が応募を避ける結果を招くこともあります。離職は単なる個人の問題ではなく、組織としての継続的なリスク要因と捉えるべきです。
高い離職率が企業にもたらす影響例
- 採用・教育コストの増大|繰り返される新人育成による負担
- 生産性の低下|業務の属人化とノウハウの喪失
- 残存社員のモチベーション低下|負担集中による不満の蓄積
- 企業イメージの悪化|「辞めやすい会社」としてのレッテル
- 優秀人材の応募回避|求人市場での評価低下による人材難
同じ理由で辞める人が続く職場の特徴
退職理由が特定のパターンで繰り返される場合、職場内に構造的な問題が潜んでいる可能性があります。たとえば「評価されない」「上司との関係がつらい」「育成体制がない」といった声が集中している場合、その要因は制度や風土、人事の運用方法など、管理側の体制にあることが多いです。こうした環境は、目の前の社員だけでなく、今後入社してくる人材の定着にも悪影響を及ぼすことが懸念されます。共通点に早く気づき、原因を客観的に分析する姿勢が、持続可能な職場づくりの第一歩となります。
離職理由を「本音」で知ることが職場改善の第一歩
退職者リサーチがもたらす企業へのメリット
退職者リサーチとは、第三者機関が中立の立場から退職者に対して聞き取りを行い、真の退職理由や職場環境に対する印象を収集する手法です。企業が直接聞いても得られにくい「本音」を引き出すことで、管理職の対応、評価制度の不公平感、過重労働など、根本的な課題が明確になります。これにより、単なる一時的な対症療法ではなく、長期的な職場改善・制度見直しにつながる具体的なデータが得られます。内部では見えにくい問題点を可視化し、離職率の低下と人材の定着強化に貢献する実践的な手段です。
従業員が「本音」を語らない理由とは
退職時の面談で本音が語られない背景には、相手が上司や人事担当者であることへの心理的な抵抗があります。「最後に波風を立てたくない」「悪者にされたくない」といった気持ちから、本当の不満や指摘を伏せたまま辞める人が多いのが実情です。特に、パワハラや評価への不満、人間関係の問題は、直接口に出しづらく、表面的には「家庭の事情」や「キャリアアップ」といった言い換えで処理されてしまいます。このような隠れた離職理由を掘り起こすには、利害関係のない第三者の存在が必要不可欠です。
企業改善に直結するデータの可視化
退職者リサーチで得られた定性的な意見は、項目ごとに分類・集計することで、社内の問題傾向を視覚的に把握することができます。たとえば、「評価制度への不満」が複数回指摘されていれば、管理職の評価基準やフィードバック体制の見直しが急務と判断できます。また、「残業時間の多さ」や「成長実感の欠如」などの傾向があれば、制度改善や教育体制の再構築にもつながります。数値だけでは見えない“声”を整理・構造化することで、企業の課題を明確にし、再発防止策や改善施策の精度を高めることができます。
企業改善に直結するデータ
- 評価制度への不満の集中|管理職評価の基準・運用の見直しが必要
- 残業時間の多さの指摘|業務負荷と就業管理体制の再検討
- 成長実感の欠如|教育・キャリア支援体制の強化が求められる
- 職場風土や人間関係の問題|マネジメント層の行動変革が課題
- 傾向の構造化|改善施策の優先順位づけと進捗管理に活用可能
退職者リサーチを成功させるための実施ステップと留意点
調査の進め方と効果的なヒアリング手法
退職者リサーチは、退職者本人に対して電話やオンライン面談、メールアンケートなどでヒアリングを行うのが一般的です。調査の目的や背景を丁寧に説明したうえで、自由回答形式や選択肢形式を組み合わせ、忖度なく意見を述べてもらえる環境を整えることが重要です。特に中立的な立場にある外部の調査機関が対応することで、本音を引き出しやすくなります。また、回答者の匿名性を確保したり、報復などの懸念がないことを伝える配慮も必要です。調査は単なる情報収集ではなく、信頼関係に基づいたコミュニケーションと位置づけることが成功のカギとなります。
調査実施の際に注意すべきポイント
退職者リサーチを実施する際には、対象者のプライバシーや感情に十分配慮することが前提です。無理に回答を求めたり、過去の出来事を過度に詮索するような質問は避けるべきです。また、得られた回答はあくまで「個人の感じ方」であることを踏まえ、他のデータや複数の意見と照合して分析する必要があります。加えて、調査結果をそのまま特定部署や個人の責任に直結させてしまうと、社内に不信感や反発を生むリスクもあります。結果は冷静かつ客観的に受け止め、組織全体の改善に活かす視点が求められます。
調査結果を活用するための社内体制づくり
退職者リサーチで得られた情報を効果的に活用するには、調査結果を受け止める側の「体制」も整える必要があります。たとえば、人事部門や経営層だけでなく、現場の管理職にも適切にフィードバックを行い、問題意識を共有することが重要です。また、調査結果を基に改善策を検討・実行するプロセスをルール化し、進捗管理を含めたPDCAを社内で回す体制を整えることで、リサーチが一過性で終わらず、持続的な改革につながります。従業員の声を「聞くだけ」で終わらせない実行力が、企業体質を変える鍵となります。
調査の質と効果を高めるための外部リソースの使い方
専門調査機関に依頼するメリット
退職者リサーチを社内で実施することは可能ですが、客観性や中立性、情報開示への安心感という点では、外部の専門機関に依頼するメリットが大きいです。第三者であれば、退職者も忖度なく本音を話しやすくなり、回答の質も向上します。また、調査に特化した専門家が対応することで、ヒアリング項目の設計やデータ整理も精度高く行われ、社内での活用もしやすい形でフィードバックされます。外部視点からの分析や改善提案を得られることで、調査結果が実際の職場改革に直結する可能性も高まります。
専門家によるアフターフォローが改革の質を高める
退職者リサーチの本当の価値は、「調査結果をどう活かすか」にあります。多くの専門調査機関では、リサーチ後に丁寧なアフターフォローが行われ、結果を読み解いたうえでの分析レポートや改善提案の提供が受けられます。たとえば、指摘の多かった部署に対する具体的な改革案や、制度見直しの優先順位、マネジメント層へのフィードバックの進め方など、社内で実践可能なアクションまで支援してくれるのが大きな強みです。一過性の調査に終わらせず、継続的な組織改善につなげるには、このようなアフターサポートのある調査会社を選ぶことが成功への近道です。
調査業者選びで失敗しないためのポイント
調査会社を選ぶ際には、過去の実績、顧客企業の規模・業種への対応力、調査方法の透明性を必ず確認しましょう。ヒアリングスキルや報告書の質も重要な評価基準です。また、守秘義務契約や個人情報保護に関する体制が整っているかどうかも信頼性を測る指標になります。さらに、単なる結果の提示にとどまらず、改善案まで提案してくれるかどうかもポイントです。形式だけの調査で終わらせず、実効性のあるリサーチを実現するためには、企業の課題に寄り添えるパートナーの選定がカギとなります。
無理なく導入できるリサーチ依頼の基本と予算感
相談からはじまる導入の第一歩
専門会社では、初回の無料相談を受け付けています。この相談では、現在の離職状況や課題感、調査の目的をヒアリングしたうえで、最適な調査方法や対象者の範囲などをアドバイスしてくれます。相談時点で無理に契約を迫られることはなく、情報整理と検討の材料として活用する企業も少なくありません。初回相談では、調査の進め方やデータの活用イメージ、秘密保持体制などについても確認できるため、調査の導入を検討している企業にとって安心できるファーストステップとなります。
目的と課題に応じた柔軟なプラン設計
退職者リサーチには、アンケート形式の簡易調査から、個別面談による深掘り調査まで、目的に応じた多様なプランが用意されています。たとえば、全社的な傾向を把握したい場合は集計型の定量調査が有効であり、個別の退職者から具体的な背景を掘り下げたい場合は面談形式が適しています。また、管理職の離職やハラスメント疑惑があるケースでは、調査設計もより慎重な配慮が必要です。企業の規模や抱える課題に合わせた柔軟なプラン選択が、調査の成果を左右します。
明瞭な料金設定で安心して依頼できる体制を
退職者リサーチの費用は、調査対象者数・方法・報告形式によって変動しますが、一般的には数万円前後~数十万程度が相場です。調査会社によっては、複数名のパッケージ料金や年間契約プランも用意されており、継続的な改善活動として導入する企業も増えています。見積り依頼の際には、対象人数、希望する調査の深さ、報告の納品形式などを具体的に伝えることで、より適切な価格と内容の提案が得られます。明瞭な料金設定と納得の説明を行う業者を選ぶことが、信頼できる依頼先選びの第一歩です。
探偵法人調査士会公式LINE
探偵依頼ガイドでは、LINEからの無料相談も可能です。お仕事の関係や電話の時間がとれない場合など、24時間いつでも相談可能で利便性も高くご利用いただけます。
退職者リサーチの結果が企業改善に結びついた事例
退職者の声をきっかけに人事制度を刷新した事例
あるIT企業では、離職理由が「キャリアアップ」とされるケースが続き、真因を探るために退職者リサーチを実施。調査の結果、実際には「評価が不透明」「成果が認められない」といった不満が多く寄せられていたことが明らかになりました。これを受けて人事制度の見直しが行われ、評価基準の明文化やフィードバック制度の強化が導入されました。その後、離職率は大幅に改善し、従業員の満足度や定着率も上昇。退職者の本音を活かした改革が、企業全体の働きやすさに繋がった成功例です。
マネジメント改善に活かされたリサーチ結果
ある製造業の中堅企業では、特定の部署で離職が相次いでいたため、第三者による退職者ヒアリングを導入しました。調査の結果、上司の威圧的な態度や相談しにくい雰囲気が主な離職原因であることが明らかになりました。この結果をもとに、管理職向けのコミュニケーション研修や1on1面談の導入など、マネジメント改善のための施策が実施されました。その結果、半年後には当該部署の離職率が半減し、原因を明確にして対策につなげたことが成功の大きな要因となりました。
制度改革の方向性をデータで裏付けた例
あるサービス業の企業では、若手社員の離職が続いており、原因の特定が難しい状態が続いていました。そこで退職者リサーチを実施した結果、「成長の機会がない」「研修が実態に合っていない」といった声が多く挙がりました。この調査結果を受けて、企業では育成プログラムの全面的な見直しとキャリア支援制度の整備を行いました。結果的に若手社員の満足度が向上し、採用広報にも活用できる実績が生まれました。データに基づく判断が、制度改革の方向性を明確にした好事例です。
よくある質問(FAQ)
退職後に連絡しても失礼ではないですか?
退職者に対して後日連絡を取ることに心理的な抵抗を感じる企業もありますが、適切な配慮と目的説明を伴えば失礼にはあたりません。第三者機関を通じて実施する場合は、連絡内容も丁寧に設計されており、調査目的や回答の自由性、匿名性が明示されます。その結果、退職者側も安心して協力できる体制が整います。むしろ「企業が改善のために動いている」という姿勢が伝わることで、良好な関係を保ちながら率直な意見を聞き出せる機会となります。
どのタイミングで調査を依頼するのがベストですか?
退職者リサーチは、退職後できるだけ早い段階で実施するのが理想です。1〜2か月以内であれば、職場での記憶が新鮮で、より具体的なエピソードや感情が聞き出しやすくなります。一方で、ある程度時間が経ってからでも、感情的なわだかまりが落ち着いており、客観的な意見が得られることもあります。離職理由の傾向を把握したい企業では、一定期間ごとにまとめて実施する方式も有効です。目的に応じた実施タイミングを調整することが、調査の有効性を高めるポイントです。
結果を公表すると社内に不安が生じませんか?
調査結果の社内共有には慎重な姿勢が求められますが、適切に取り扱えば組織改善の意識を高める良い機会となります。具体的な個人名を挙げることなく、傾向や改善点としてフィードバックすることで、現場の理解と納得を得られます。むしろ「社員の声を受け止め、行動している会社」としての信頼が高まり、エンゲージメント向上にもつながるケースが多く見られます。結果の共有方法も調査会社のアドバイスを受けながら進めると安心です。
従業員の「本音」を企業の未来につなげるために
退職者リサーチは、単なる離職理由の確認にとどまらず、職場環境や組織運営に潜む課題を明らかにする貴重な手段です。従業員の声に耳を傾け、改善へとつなげる姿勢は、企業文化や採用ブランドにも大きな影響を与えます。特に人材の定着が課題となる今、離職を「終わり」ではなく「改善のきっかけ」と捉え、継続的な組織改革につなげていく視点が重要です。専門家の力を借りながら本音を見える化し、それを制度や風土づくりに反映することで、より強くしなやかな組織づくりが可能になります。
※当サイトでご紹介している相談内容はすべて、探偵業法第十条に準じて、個人情報の保護に十分配慮し、一部内容を変更・修正のうえ掲載しています。法人企業向けガイドは、企業活動におけるリスク対策や内部調査、信用調査など、法人が探偵を活用する際に必要な情報を分かりやすく整理・提供するコンテンツです。安心・合法な調査の進め方をサポートします。
週刊文春に掲載 2025年6月5日号
探偵法人調査士会が運営する「シニアケア探偵」が週刊文春に掲載されました。一人暮らしの高齢者が増加している背景より、高齢者の見守りツールやサービスは注目されています。シニアケア探偵も探偵調査だからこそ行える見守り調査サービスを紹介していただいています。昨今、日本の高齢者問題はますます深刻さを増しています。少子高齢化の進行により、多くのご家庭が介護や見守りの悩み、相続の不安、悪質な詐欺や被害などの金銭トラブルに直面しています。「シニアケア探偵」の高齢者問題サポートは、こうした問題に立ち向かい、高齢者の皆様とご家族をサポートするために設立されました。

この記事の作成者
探偵調査員:北野
この記事は、はじめて探偵を利用される方や困りごとを解決するために探偵利用を考えている方に向けて、探偵の使い方をできるだけ分かりやすく知っていただくために調査員の目線で作成しました。探偵利用時に困っていることや、不安に感じていることがあれば、当相談室へお気軽にご相談ください。どんな小さなことでも、お力になれれば幸いです。

この記事の監修者
XP法律事務所:今井弁護士
この記事の内容は、法的な観点からも十分に考慮し、適切なアドバイスを提供できるよう監修しております。特に初めて探偵を利用される方は、有益な利用ができるようにしっかりと情報を確認しましょう。法的に守られるべき権利を持つ皆様が、安心して生活できるよう、法の専門家としてサポートいたします。

この記事の監修者
心理カウンセラー:大久保
人生の中で探偵を利用することは数回もないかと思います。そのため、探偵をいざ利用しようにも分からないことだらけで不安に感じる方も多いでしょう。また、探偵調査によって事実が発覚しても、それだけでは心の問題を解決できないこともあります。カウンセラーの立場から少しでも皆様の心の負担を軽くし、前向きな気持ちで生活を送っていただけるように、内容を監修しました。あなたの気持ちを理解し、寄り添うことを大切にしています。困ったことがあれば、どうか一人で悩まず、私たちにご相談ください。心のケアも、私たちの大切な役割です。
24時間365日ご相談受付中

探偵依頼に関する相談は、24時間いつでもご利用頂けます。はじめてサービスを利用される方、依頼料に不安がある方、依頼を受けてもらえるのか疑問がある方、まずはご相談ください。専門家があなたに合った問題解決方法をお教えします。
探偵依頼に関するご相談、探偵ガイドに関するご質問は24時間いつでも専門家がお応えしております。(全国対応)
探偵依頼に関するご相談はLINEからも受け付けております。メールや電話では聞きづらいこともLINEでお気軽にお問合せいただけます。質問やご相談は内容を確認後、担当者が返答いたします。
探偵依頼に関する詳しいご相談は、ウェブ内各所に設置された無料相談メールフォームをご利用ください。24時間無料で利用でき、費用見積りにも対応しております。
探偵法人調査士会公式LINE
探偵法人調査士会では、LINEからの無料相談も可能です。お仕事の関係や電話の時間がとれない場合など、24時間いつでも相談可能で利便性も高くご利用いただけます。