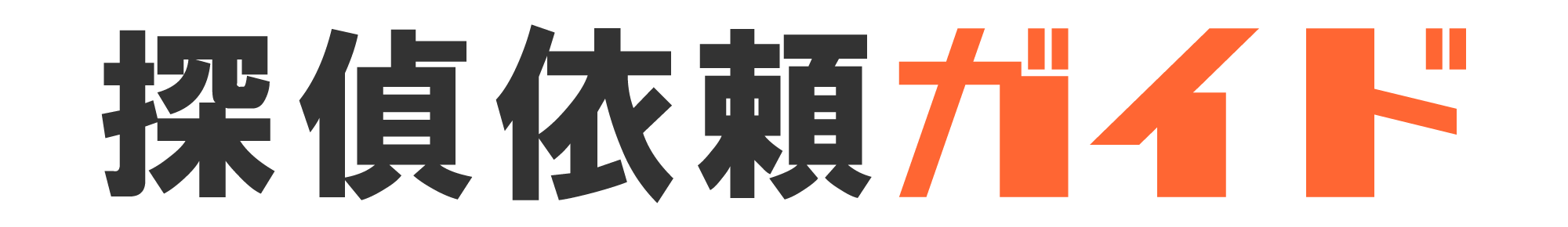サイバー攻撃や内部不正、人的ミスによる情報漏洩など、企業の情報セキュリティを脅かす要因は多岐にわたります。セキュリティ体制の強化は、今や多くの企業にとっての課題ともいえます。どれほど高価なセキュリティ製品を導入していても、実際の運用が不十分であれば意味を持たず、情報漏洩リスクは常に存在します。こうした状況において、実態調査による現状把握は対策強化の第一歩。本記事では、情報セキュリティの盲点を洗い出すための調査手法や、従業員のルール遵守状況の検証、内部不正の兆候を見逃さないための視点を整理しながら、調査によって浮き彫りになる課題とその対応方法について詳しく解説します。
- 情報セキュリティ規程が形骸化していないか
- 社内ネットワークのアクセス権が適切に管理されているか
- USBや外部ストレージの持ち出しが制限されているか
- 従業員のセキュリティ教育が継続的に行われているか
- 内部不正や情報漏洩の兆候を検知する仕組みがあるか
内部からのリスクとセキュリティ体制の実情
見えにくい内部要因が情報漏洩の主因に
近年の情報セキュリティインシデントでは、外部からのサイバー攻撃だけでなく、内部からの情報漏洩が深刻な問題として増加しています。特に、退職予定者による顧客情報の持ち出しや、従業員による不注意なメール誤送信、社内でのファイル共有設定ミスなど、「人的要因」によるトラブルが多くを占めており、企業にとって予測困難なリスクとなっています。また、セキュリティルールが社内で整備されていても、実際の運用にまで徹底されていないケースも多く、ルールと実態の乖離がリスクを拡大させています。外部攻撃に対する技術的防御策は進んでいる一方で、内部リスクへの警戒や可視化が不十分な企業が多いのが現状です。
企業が直面する情報リスクと被害の広がり
情報漏洩が一度発生すると、その被害は企業の信用を著しく損なうだけでなく、顧客離れや行政からの指導、損害賠償請求といった二次的・三次的影響を引き起こします。特に個人情報や機密データの流出は、企業ブランドへの深刻なダメージとなり、回復には多大な時間とコストを要します。中小企業であっても、取引先からの信頼を失うことで事業存続に直結するケースも珍しくありません。さらに、社内での情報取扱いへの緊張感が低下していれば、同様のトラブルが繰り返されるリスクもあります。こうした現実を受け、セキュリティ対策は「導入すること」ではなく、「継続的に機能しているか」を検証する段階へと進んでいるのです。
情報漏洩が企業にもたらす具体的な影響
- 顧客離れと売上減少|漏洩により信頼が失われ、取引継続を見直されるケースが多発
- 行政指導や罰則の対象化|個人情報保護法違反などで監督官庁からの処分を受けるリスク
- 損害賠償請求による財務圧迫|被害者からの集団訴訟などで多額の賠償責任を負う可能性
- ブランドイメージの失墜|一度の事件が長期にわたって企業の評判に影響を及ぼす
- 社内士気の低下と人材流出|情報管理の不備が従業員の不安と不信感を招き、離職に波及
形式だけの対策から実態把握へシフトする必要性
多くの企業では、情報セキュリティ対策として規程やマニュアル、教育資料を整備しているものの、それが実際に社内で守られているかは確認されていないことが少なくありません。特に日常業務の中で従業員がどれだけルールを意識しているか、アクセス権限の管理が形骸化していないか、USBメモリの利用制限が機能しているかといった運用実態の把握ができていない企業も多いのが現状です。形だけの制度に依存したままでは、リスクの本質が見えず、重大な漏洩事故が起きたときに「なぜ防げなかったのか」という問いに答えることができません。形式ではなく、実態に即した対策こそが、これからの情報セキュリティには求められています。
ルールと運用の乖離を明らかにする実態調査の意義
情報セキュリティ対策の「実際」を見える化する調査
情報セキュリティ対策において、最も見落とされがちなのが「ルールと実態の乖離」です。社内に情報管理のマニュアルやポリシーが存在していても、それが日常業務で適切に運用されているかどうかを把握できていない企業が少なくありません。実態調査では、アクセスログや端末利用履歴、外部メディアの使用状況、共有フォルダへの無断アクセス、メール送信の宛先チェックなど、実際の業務の中で潜在的なリスクが存在していないかを客観的に確認します。また、調査によって見えてきた運用の甘さを具体的な数値や証拠として記録することで、経営層や外部関係者への説明責任も果たすことができます。
情報漏洩や不正の予兆を捉えるための証拠とは
情報漏洩の兆候は、決して派手な事件として現れるものばかりではありません。たとえば、特定の社員が不自然な時間帯にログインしている、外部ストレージの使用頻度が急増している、業務に関係のない大量の印刷が行われている、といった行動パターンに不正の兆しが表れることがあります。こうした動きを把握するには、ログデータや利用記録を細かく監視し、変化を検知するための仕組みが不可欠です。調査によってこれらの証拠を収集・蓄積することで、問題が大きくなる前に対応が可能となります。また、社員教育や制度改善に活用できるリアルな情報としても、証拠の持つ意味は非常に大きいといえます。
情報漏洩リスクの兆候として確認すべき行動パターン
- 深夜や休日の不審なログイン記録|業務時間外のアクセスが継続している場合は注意が必要
- 外部ストレージの利用急増|USBやクラウドへの頻繁なデータ転送は持ち出しリスクのサイン
- 不要な大量印刷の発生|閲覧制限のある文書を出力し、持ち出す動きがある可能性がある
- 共有フォルダへの過剰アクセス|必要以上に機密ファイルを開いている履歴がある場合は監視対象
- 業務外サイトへのアクセス履歴|外部との情報交換や不審なアップロードの兆候が見られることもある
調査によって対策の優先順位が明確になる
実態調査のもう一つの意義は、現状のセキュリティ体制における「本当に改善すべきポイント」が明確になる点にあります。たとえば、セキュリティソフトは導入されていても、運用管理者のチェックが形式化していたり、アクセス制限が形だけになっていたりするなど、人的な運用面の問題が見えてくることがあります。調査により、どこにリスクが集中しているのかを可視化することで、限られた時間と予算の中で効果的に対策を講じるための優先順位が明確になります。対策の「効率」と「説得力」を両立させるうえで、調査に基づく客観的な根拠は企業にとって極めて重要です。
社内対応で見逃しがちな情報リスクへの視点
社内でできる情報セキュリティの実態把握方法
企業が自力で情報セキュリティの実態を把握する手段としては、ログイン記録の確認やアクセス履歴の点検、社内アンケートによる情報リテラシーの現状把握などが挙げられます。セキュリティソフトが提供する管理ツールを活用し、USBの使用履歴や外部サイトへのアクセス状況を定期的にチェックすることで、リスクの兆候をつかむことができます。また、部署ごとにセキュリティルールが適用されているかを検証するための内部監査も、初期段階の自衛策として有効です。特別な設備を導入しなくても、社内リソースと管理意識を工夫することで、一定の情報収集と管理の質は保てます。
自己対応の利点と見過ごされやすい問題点
自己対応のメリットは、外部コストをかけずにすぐに着手できる点にあります。社内の状況を最もよく理解している担当者が直接対応にあたることで、現場との連携もスムーズに進みます。しかしその反面、調査の網羅性や分析精度には限界があり、見落としや主観による誤認が生じやすい点も注意が必要です。特に、業務上の上下関係や組織的な配慮が働くことで、不正の兆候が黙殺されたり、都合の悪い事実が隠される可能性も否定できません。結果として、「見えている範囲」だけを根拠に判断してしまい、本質的なリスクを取りこぼしてしまう危険性があります。
自己解決が逆にリスクを増幅させるケースとは
社内だけで情報セキュリティ問題を解決しようとした結果、かえって状況を悪化させてしまうケースも存在します。たとえば、非公式な調査によって従業員の信頼を損ねたり、証拠を不適切に扱ったことで法的に無効になったりすることがあります。さらに、問題の兆候が明確になったにもかかわらず、組織内の判断で対応を見送った場合、その後に発覚した情報漏洩が「隠蔽」と受け止められ、社会的批判を受ける可能性もあります。情報管理の問題は、対応の姿勢そのものが企業の評価に直結します。社内リソースの限界を正確に把握し、必要に応じて第三者の支援を受ける判断力が、結果的に最も堅実な経営判断につながるのです。
高度化する情報リスクに対し外部知見をどう活かすか
専門家による情報セキュリティ調査の具体的アプローチ
情報セキュリティの実態調査を専門家に依頼することで、企業は内部では見落としがちなリスクや構造的な課題を正確に把握することが可能になります。専門家はアクセスログの分析、USB使用状況の監査、社員の操作履歴の記録確認、監視カメラ映像との照合などを通じ、デジタルと物理の両面からリスクの所在を洗い出します。また、ヒアリングや匿名アンケートによって従業員の情報リテラシーや運用遵守度を数値化し、実態に即した改善案を提案してくれる点も大きな強みです。外部からの視点が加わることで、企業は「見えていなかった部分」の課題にも気付くことができます。
調査後の是正提案と継続的な改善サイクルの構築
専門家による調査は、単なる現状把握にとどまらず、得られた結果に基づく改善提案を含めた「実行支援型」の支援が可能です。具体的には、脆弱性のあるルールや管理手順の見直し、教育体制の再構築、アクセス権限の適正化など、企業に応じた再発防止策が示されます。また、調査後も定期的なフォローアップや再評価を行うことで、PDCAサイクルを構築し、情報セキュリティ体制を段階的に強化していくことが可能です。こうした外部との連携により、セキュリティを「一度整えれば終わり」ではなく「継続して改善し続けるもの」として位置づけることができ、結果として企業の信頼性向上にも寄与します。
専門家に依頼する際の利点と注意すべき点
専門家に調査を依頼する最大のメリットは、客観性と技術力に裏付けられた対応が得られることです。社内の事情に左右されることなく、公平な視点からリスクを評価・報告してくれるため、経営層も安心して改善判断を下すことができます。また、専門家が保有する専門ツールやノウハウにより、社内では実現困難な調査領域にも対応できます。一方で、注意すべき点としては、業者選定時に信頼性や実績をしっかり確認すること、調査内容と費用のバランスを事前に見極めることが挙げられます。目的に応じた適切なスコープ設定を行い、必要な調査だけを無駄なく依頼することが、費用対効果の高い活用につながります。
企業に適した外部調査活用の実践ステップ
初回無料相談で現状の課題を整理する
多くの調査機関では、法人向けに無料の初回相談を設けており、情報セキュリティに関する悩みや課題を気軽に相談できます。初回相談では、ヒアリングを通じて現状のリスクや体制の不備が明らかにされ、調査の必要性や方向性が客観的に整理されます。調査を本格的に依頼するかは、この時点で判断可能であり、無理な勧誘は一切行われません。相談の段階から守秘義務が適用されるため、社外への情報漏洩リスクもなく、安心して利用することができます。初回のやりとりで、信頼できるパートナーであるかどうかを見極めることができる点も大きな利点です。
自社の状況に合った柔軟な調査プランの選定
専門家による情報セキュリティ調査は、調査対象や目的に応じて多様なプランが用意されています。たとえば、アクセスログや操作履歴を短期でチェックする簡易診断プラン、従業員意識調査や管理体制監査を含む総合調査プラン、特定部門に絞った部分調査など、状況に応じてカスタマイズが可能です。企業規模や業種によってセキュリティの脆弱ポイントは異なるため、画一的な内容ではなく、必要最小限の費用で最大の成果を得られるプラン設計が重要です。必要に応じて段階的に調査を進める「ステップ式」対応も可能なため、コスト面の調整にも柔軟に対応できます。
料金の目安と見積もり依頼の流れ
調査の料金は、調査範囲・規模・日数・報告の形式などによって異なりますが、目安としては簡易診断で5万〜10万円程度、詳細な組織全体調査では30万〜100万円前後のケースもあります。見積もりは初回相談の内容に基づいて提示され、調査項目ごとに費用内訳が明示されるため、納得した上で契約に進むことができます。契約締結後は、調査計画に沿って進行し、報告書の提出をもって完了となる流れです。アフターフォローや改善提案を含めた継続的支援も別途契約可能であり、調査結果を最大限に活用する体制も整えられます。
探偵法人調査士会公式LINE
探偵依頼ガイドでは、LINEからの無料相談も可能です。お仕事の関係や電話の時間がとれない場合など、24時間いつでも相談可能で利便性も高くご利用いただけます。
実務の中で発見されたセキュリティ課題とその克服
社内ネットワークのアクセス不備を可視化し改善に成功
あるIT系企業では、社内ファイルサーバーにアクセス制限が設定されているにもかかわらず、複数の部署で不要なファイル閲覧が可能な状態が続いていました。社員の情報モラルは高いと信じていたため見過ごされていたこの問題を、第三者調査によって発見。アクセスログの解析を通じて、誰が、いつ、どのファイルにアクセスしたかが明確になり、情報分類と権限設定の再設計が行われました。その結果、セキュリティリスクが著しく低下し、取引先からの評価も向上しました。
外部記憶媒体の利用実態を把握し内部統制を強化
製造業を営む企業では、外部ストレージ機器(USB・外付けHDD)の利用が社員に広く認められていましたが、使用記録が残されておらず、リスクが高まっていました。専門家による調査でUSB使用の記録を洗い出したところ、一部の部署で頻繁なデータ持ち出しが確認されました。すぐに利用制限と申請制の導入、さらに自動記録システムの構築が行われたことで、内部統制が大きく改善。社員への教育効果も高まり、社内の情報セキュリティ意識が飛躍的に向上しました。
従業員の情報管理意識調査から教育体制を再設計
人材派遣会社では、派遣先企業の情報を扱う立場から高い情報リテラシーが求められていましたが、社内教育が形式的になっており、実態との乖離が懸念されていました。専門家による匿名意識調査を実施した結果、約3割の社員が「情報管理に自信がない」と回答。そのデータをもとに教育内容が刷新され、現場に即した事例ベースの研修が導入されました。結果として、トラブル件数の減少と社内の情報モラルの底上げが実現しました。
よくある質問(FAQ)
Q.社内に知られずに調査を行うことは可能ですか?
A.はい、可能です。情報セキュリティ調査においては、従業員に調査実施を事前に知られずに実行する「覆面型調査」が一般的に行われています。調査機関は、対象者や部署に影響を与えないよう慎重に進めるノウハウを持っており、ログの取得やアクセス記録の分析もシステムに負担をかけることなく行われます。また、調査計画の段階でクライアント企業と綿密に打ち合わせを行い、調査対象・範囲・期間・方法を明確化するため、想定外の混乱が発生することはありません。
Q.調査内容は法的に問題ないのですか?
A.調査機関が行うセキュリティ調査は、すべて個人情報保護法や労働法などの関連法令に則って実施されます。たとえば、社内ネットワーク上のアクセス履歴確認やUSB使用記録の抽出は、業務機器やシステムの管理権限を持つ企業側が正当な理由に基づいて行うものです。調査開始前には必ず法務部や顧問弁護士と確認を行い、法的リスクが発生しないよう配慮されています。情報漏洩や内部不正が起きてからでは遅いため、合法かつ適正な手段でリスクの把握を行うことが重要です。
Q.調査後に企業側が何をすれば良いですか?
A.調査後には、調査機関から提出される報告書をもとに、改善点の洗い出しと対策実行が求められます。報告書にはリスク箇所や運用上の課題が具体的に示されており、それに基づきアクセス権限の見直しや教育の再構築、管理手順の改善などを進めます。また、再調査や定期的なモニタリングを導入することで、改善の効果を継続的に検証し、長期的なリスク対策につなげることが可能です。必要に応じて調査機関が再発防止策の提案も行ってくれるため、実行フェーズでも専門家の知見を活用できます。
「見えていないリスク」に向き合う姿勢が企業を守る
情報セキュリティ対策は、単にルールやシステムを導入するだけでは不十分であり、日常の業務運用が実際に安全かどうかを定期的に見直す姿勢が求められます。特に内部要因による情報漏洩や不正は、形式的な体制だけでは発見が困難であり、実態調査による可視化こそがリスク低減の出発点となります。社内対応には限界があり、感覚や経験に頼った判断だけでは経営判断として不十分です。第三者による専門調査を適切に活用することで、企業は確かな根拠を持った改善策を実行に移すことができ、取引先や顧客に対しても信頼を示す材料となります。今後、企業の社会的責任が問われる場面では、「対策をしたか」ではなく「実効性のある対策を続けてきたか」が問われる時代です。早い段階での実態把握こそが、リスクに強い組織づくりの第一歩です。
※当サイトでご紹介している相談内容はすべて、探偵業法第十条に準じて、個人情報の保護に十分配慮し、一部内容を変更・修正のうえ掲載しています。法人企業向けガイドは、企業活動におけるリスク対策や内部調査、信用調査など、法人が探偵を活用する際に必要な情報を分かりやすく整理・提供するコンテンツです。安心・合法な調査の進め方をサポートします。
週刊文春に掲載 2025年6月5日号
探偵法人調査士会が運営する「シニアケア探偵」が週刊文春に掲載されました。一人暮らしの高齢者が増加している背景より、高齢者の見守りツールやサービスは注目されています。シニアケア探偵も探偵調査だからこそ行える見守り調査サービスを紹介していただいています。昨今、日本の高齢者問題はますます深刻さを増しています。少子高齢化の進行により、多くのご家庭が介護や見守りの悩み、相続の不安、悪質な詐欺や被害などの金銭トラブルに直面しています。「シニアケア探偵」の高齢者問題サポートは、こうした問題に立ち向かい、高齢者の皆様とご家族をサポートするために設立されました。

この記事の作成者
探偵調査員:北野
この記事は、はじめて探偵を利用される方や困りごとを解決するために探偵利用を考えている方に向けて、探偵の使い方をできるだけ分かりやすく知っていただくために調査員の目線で作成しました。探偵利用時に困っていることや、不安に感じていることがあれば、当相談室へお気軽にご相談ください。どんな小さなことでも、お力になれれば幸いです。

この記事の監修者
XP法律事務所:今井弁護士
この記事の内容は、法的な観点からも十分に考慮し、適切なアドバイスを提供できるよう監修しております。特に初めて探偵を利用される方は、有益な利用ができるようにしっかりと情報を確認しましょう。法的に守られるべき権利を持つ皆様が、安心して生活できるよう、法の専門家としてサポートいたします。

この記事の監修者
心理カウンセラー:大久保
人生の中で探偵を利用することは数回もないかと思います。そのため、探偵をいざ利用しようにも分からないことだらけで不安に感じる方も多いでしょう。また、探偵調査によって事実が発覚しても、それだけでは心の問題を解決できないこともあります。カウンセラーの立場から少しでも皆様の心の負担を軽くし、前向きな気持ちで生活を送っていただけるように、内容を監修しました。あなたの気持ちを理解し、寄り添うことを大切にしています。困ったことがあれば、どうか一人で悩まず、私たちにご相談ください。心のケアも、私たちの大切な役割です。
24時間365日ご相談受付中

探偵依頼に関する相談は、24時間いつでもご利用頂けます。はじめてサービスを利用される方、依頼料に不安がある方、依頼を受けてもらえるのか疑問がある方、まずはご相談ください。専門家があなたに合った問題解決方法をお教えします。
探偵依頼に関するご相談、探偵ガイドに関するご質問は24時間いつでも専門家がお応えしております。(全国対応)
探偵依頼に関するご相談はLINEからも受け付けております。メールや電話では聞きづらいこともLINEでお気軽にお問合せいただけます。質問やご相談は内容を確認後、担当者が返答いたします。
探偵依頼に関する詳しいご相談は、ウェブ内各所に設置された無料相談メールフォームをご利用ください。24時間無料で利用でき、費用見積りにも対応しております。
探偵法人調査士会公式LINE
探偵法人調査士会では、LINEからの無料相談も可能です。お仕事の関係や電話の時間がとれない場合など、24時間いつでも相談可能で利便性も高くご利用いただけます。