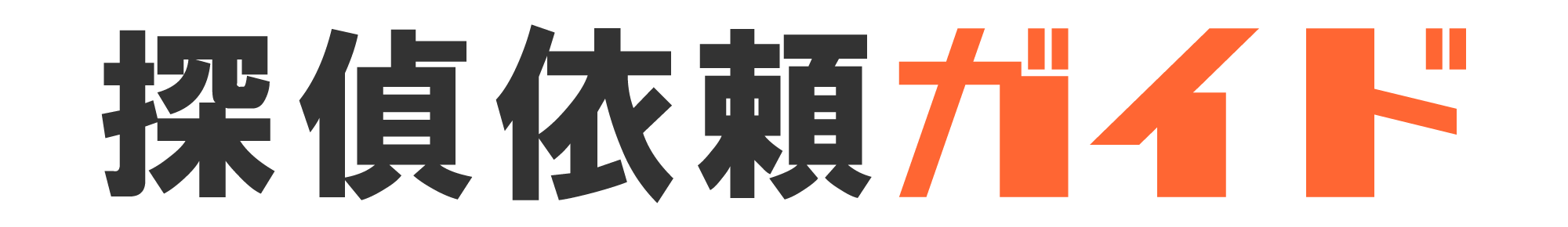企業の信頼と資産を脅かすリスクの一つが、従業員や関係者による内部犯罪です。横領、情報漏洩、社内設備の私的流用など、企業の資産が侵害される事例は年々増加しており、発覚時には甚大な損害や社会的信用の失墜につながります。こうしたリスクを防ぐためには、内部統制の強化に加え、第三者による客観的な調査や証拠収集が重要です。本記事では、内部犯罪の代表的な手口とその傾向、企業が自らできる対策、探偵などの専門家に依頼するメリットと注意点を詳しく解説いたします。企業防衛の第一歩として、内部犯罪対策の基本を押さえておきましょう。
- 内部犯罪が発生しやすい組織環境とは
- 不正を見抜くための兆候やサイン
- 社内調査と外部調査の違い
- 証拠収集における注意点と法的配慮
- 専門家に依頼するメリットとタイミング
企業を脅かす内部犯罪の現状とその背景
増加傾向にある内部犯罪とその特徴
企業における内部犯罪は、かつてはまれな問題とされていましたが、近年では大小を問わずさまざまな業種で頻発しています。横領や着服、情報漏洩、不正アクセスなどその手口は多様化しており、内部関係者による犯行であるがゆえに、発見が遅れるケースも多いのが現状です。特に、中小企業では内部統制が十分に機能しておらず、不正が長期間にわたって見過ごされることも珍しくありません。犯行の動機は、経済的困窮、職場への不満、業務管理の甘さなどが挙げられ、これらが複合的に絡み合って犯罪を引き起こします。企業にとって内部犯罪は、単なる金銭的損失にとどまらず、社会的信用の失墜や社員の士気低下をも招く深刻な問題となっているのです。
見逃されやすい内部犯罪のリスクとは
内部犯罪の多くは、外部からは見えにくい点に最大のリスクがあります。犯行者が日常的に社内に存在し、業務に精通しているため、痕跡をうまく隠しながら不正を行うことが可能です。また、内部通報制度があっても、社内の人間関係や報復への懸念から通報がなされないケースも多く、実際に不正が明るみに出るまでに長い時間を要することがあります。企業が被る被害は、金銭的損失だけでなく、情報漏洩による取引先の信用失墜、従業員全体への悪影響など多岐にわたります。特にデジタル化が進む現在では、データの持ち出しやアクセスログの改ざんなど、高度化・巧妙化した手法も増えており、経営層がリスクの存在を過小評価していると、大きな損害につながりかねません。早期発見と抑止が今後の企業防衛の鍵となります。
見過ごされがちな内部犯罪の代表的リスク
- 社内人脈による隠蔽|同僚や上司の庇護により、不正が見逃されやすくなる
- 通報のためらい|報復や職場の空気を恐れ、内部通報制度が機能しない
- ログ改ざんの巧妙化|IT知識を活かしてアクセス履歴を消去・改変する手口
- 長期にわたる損失|発覚までに時間がかかり、累積被害が膨大になる
- 信用失墜の連鎖|情報漏洩や不正発覚により、取引先からの信頼を喪失する
企業が取り組むべき基本的なリスク対策
企業が内部犯罪を防ぐためにまず必要なのは、「不正をさせない」環境づくりです。そのためには、職務の分離や定期的な監査、情報アクセスの権限管理といった内部統制の徹底が求められます。また、従業員が安心して不正を報告できる通報制度の整備や、倫理意識を高めるための教育・研修も有効です。さらに、経営陣が日頃から現場の動きに目を配り、社員との信頼関係を築く姿勢も重要です。表面的な制度やマニュアルだけでは、従業員の行動変容にはつながりません。内部犯罪は、一度発生するとその対応に多大なコストと時間がかかります。だからこそ、未然に防ぐための組織づくりとリスクマネジメントの強化が、すべての企業にとって喫緊の課題となっています。
不正の実態を明らかにするための証拠の意味と活用
内部不正調査における証拠収集の必要性
企業内で不正が疑われる場合、最も重要となるのはその行為を裏付ける「証拠」を確実に押さえることです。内部犯罪の多くは密室的な状況で行われ、明確な証拠がなければ処分や法的措置を取ることは困難です。証拠が不十分なまま処分に踏み切った場合、逆に不当解雇や名誉毀損で企業が訴えられるリスクもあります。そのため、内部調査ではデジタルデータのログやメール履歴、監視カメラ映像、関係者の証言などを法的に適切な方法で収集・保管する必要があります。証拠があれば、不正の有無を客観的に判断できるだけでなく、再発防止策の立案にもつながります。また、従業員に対して「企業が不正を見逃さない」というメッセージを発信することにもなり、組織内の規律維持に貢献します。
信頼できる証拠とは何か?判断基準と注意点
証拠として活用するためには、その内容が「客観性」「信頼性」「適法性」を備えている必要があります。たとえば、社内の監視カメラ映像は客観的で時系列も明確なため、非常に有力な証拠となり得ます。電子メールやチャットの履歴も、発言の内容やタイミングが明確で、内部のやり取りを示す重要な手がかりとなります。ただし、これらの情報を収集する際には、個人情報保護法や労働関連法規に抵触しないよう配慮が必要です。違法な手段で得た証拠は、たとえ内容が正しくても訴訟等で使用できない場合があります。そのため、調査を行う際には法的な知識を持った専門家と連携し、記録の取得と保管に慎重を期すことが求められます。証拠は単なる記録ではなく、企業が正当な対応を行うための防衛手段です。
信頼性の高い証拠の判断基準と取得時の注意点
- 客観性の確保|映像やログなど、事実を裏付ける再現可能なデータであること
- 信頼性の維持|編集や改ざんのない、取得日時や出所が明確な記録であること
- 適法性の遵守|個人情報保護法や労働法を遵守し、合法な手段で収集されていること
- 保管と管理の厳格化|証拠が破損・紛失しないよう、適切な形式と環境で保管すること
- 専門家との連携|証拠の取得・使用の正当性を担保するために専門家の関与が重要
調査結果を活用した企業対応と再発防止策
集められた証拠は、単に不正を明らかにするためだけでなく、その後の社内対策や教育強化にも役立てることができます。たとえば、不正が起きた部署の業務フローを見直したり、監視体制の強化、通報制度の再整備など、再発防止のための具体策を打ち出すための根拠となります。また、従業員に対して事例をもとに研修を実施することで、企業としてのコンプライアンス意識を高め、社内全体の意識改革を促すことも可能です。証拠は問題解決の「終点」ではなく、企業改革の「始点」として機能します。調査によって明らかになった事実をもとに、経営陣が組織全体の透明性と健全性を高める対策を講じることで、将来的なリスクを最小限に抑えることができます。
企業内で行える調査とその限界を見極める
自社で実施可能な不正調査の方法とは
企業が自ら内部不正を調査する場合、まず実施できるのは社内の監視カメラ映像の確認や、勤務記録・出退勤ログの分析、社内ネットワークのアクセス履歴の調査などです。また、関係者への聞き取りや業務日誌の照合といったヒアリングも初期対応として有効です。これらの方法は比較的コストがかからず、スピーディーに実施できる点が利点です。しかし、証拠の保全方法や調査の正当性が不十分だと、後の処分や訴訟対応で企業側が不利になる恐れもあるため、法的観点への配慮も欠かせません。
自社対応のメリットとデメリット
社内で調査を行う最大のメリットは、コストを抑えつつ迅速に対応できることです。また、内部の事情に詳しい担当者が調査を行うことで、関係者との信頼関係を維持しながら対応を進めることが可能です。しかしその反面、調査対象者と利害関係がある場合、客観性や中立性に欠ける恐れがあります。また、情報漏洩のリスクや、逆に調査対象者からの訴訟リスクも伴います。調査結果の信憑性を担保するには、社内のみに頼らず、第三者の目を取り入れる工夫が必要です。
自己解決を試みる際の注意点と限界
企業が内部不正を独自に調査しようとする際には、その手法や範囲を誤ると、かえって状況を悪化させる可能性があります。たとえば、監視の強化が従業員の不信感を生み、社内の雰囲気が悪化することが考えられます。また、本人に気づかれた場合の証拠隠滅や逆恨みによるトラブルも懸念されます。さらに、法律に抵触する形での調査(例:私物の無断調査や私生活の侵害)を行った場合には、企業側が訴えられるリスクもあります。調査を始める際には、目的と範囲を明確にし、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。
専門家の力を借りることで実現する正確で安全な不正対応
専門家による調査の実施方法と信頼性
探偵や調査士といった専門家による内部犯罪調査は、企業が自力で対応しきれない高度な調査ニーズに対応する手段として注目されています。彼らは豊富な経験と法的知識を持ち、違法性のない方法で確実な証拠を収集します。たとえば、社員の不審な行動に関する尾行調査や、外部との不正な接触履歴の確認、ITを用いたデジタル証拠の取得など、専門的な技術を駆使して実態を明らかにします。これにより、企業は証拠に基づいた適切な判断を下すことが可能となり、訴訟リスクの回避にもつながります。
調査後の報告とアフターフォローの重要性
専門家に依頼した調査が終了すると、詳細な報告書が企業に提出されます。この報告書には、調査対象の行動や関係性、取得した証拠の内容が時系列に沿って整理されており、企業がその後の処分や改善策を決定する際の重要な資料となります。また、多くの専門機関では、報告書の内容に関するアフターフォローも実施しており、調査結果の法的な扱いや今後のリスク対策について相談することができます。これにより、調査で得た情報を一過性のものにせず、企業の内部統制強化や社員教育の土台として活用することができます。
専門家に依頼するメリットと留意点
専門家に調査を依頼するメリットは、何よりも調査の信頼性と中立性にあります。社内では見つけられなかった事実や証拠を、第三者の立場から客観的に収集できることで、企業の対応がより正確かつ説得力のあるものになります。ただし、費用がかかることや、社内に調査の事実が知られることで心理的負担が生じる可能性もあるため、依頼のタイミングや目的を明確にする必要があります。また、探偵業法などの法令を遵守した信頼性のある機関を選ぶことも、成功に導く大きなポイントです。
調査依頼の手順と費用感を正しく把握する
初回相談と調査内容の明確化について
探偵事務所や調査機関では、まず初回相談を通じて企業の状況や調査の目的を明確にします。この相談は無料で実施されるケースが多く、依頼者が感じている不安や疑問を丁寧にヒアリングしたうえで、最適な調査プランが提案されます。どのような証拠を必要としているのか、調査対象者は誰か、どのような手段が適切かといった点を一緒に整理することで、無駄のない効率的な調査が可能となります。調査経験のあるスタッフが対応するため、初めての企業様でも安心して相談できます。
調査プランとカスタマイズの柔軟性
調査の内容は、企業の要望に応じてカスタマイズが可能です。たとえば、対象者の行動調査のみを行うプランや、社内のデジタルログを中心に調べるIT調査、複数部門にまたがる横断的な不正の可能性を検証する包括的な調査など、多様なオプションが用意されています。企業の規模や予算、調査範囲に応じて最適なプランが組まれるため、必要最低限の調査で最大の効果を得ることができます。また、調査の途中で内容を変更することもできる場合があり、進行に応じて柔軟な対応が受けられるのも魅力です。
費用の目安と見積もり依頼の進め方
調査費用は内容や期間、調査対象の数などにより大きく変動しますが、一般的には短期の行動調査で10万円前後、長期的または複数対象者への調査になると数十万円以上となることもあります。ただし、調査機関では必ず事前に詳細な見積もりが提示され、その内訳も明確に説明されます。依頼者としては、見積もり段階で不明点や不要と思われる項目を確認・調整することで、無駄なコストを避けることが可能です。契約前にしっかりと内容を確認し、納得した上で調査を依頼することが、安心につながります。
探偵法人調査士会公式LINE
探偵依頼ガイドでは、LINEからの無料相談も可能です。お仕事の関係や電話の時間がとれない場合など、24時間いつでも相談可能で利便性も高くご利用いただけます。
実際に調査を依頼した企業の体験とその成果
長期的な横領の発覚と再発防止への活用例
ある製造業の中堅企業では、経理担当者の使途不明金が数カ月間続いていることに気づき、外部の探偵事務所に調査を依頼しました。調査の結果、経理担当者が経費精算を不正に操作し、長期的に資金を着服していたことが明らかになりました。証拠となる帳票の改ざん記録や、防犯カメラ映像、メールのやり取りを報告書にまとめてもらい、懲戒処分とともに法的手続きへと移行しました。また、事件後は業務フローの見直しと内部監査体制の強化を図り、同様の不正を二度と起こさせない企業体制を整えました。
情報漏洩の兆候を見逃さず早期に対応した事例
IT関連企業では、新製品の開発情報が競合他社に漏れている可能性があるとの疑いから、情報の取り扱いに関与する社員数名を対象に調査を実施しました。その結果、特定の社員が退職予定であり、社外USBの持ち出しログや不審な外部との通信履歴が確認されました。企業は速やかに当該社員のアクセス権を制限し、さらに詳細な調査を進めることで漏洩を未然に防ぐことができました。調査後は情報管理体制の見直しが行われ、社員への研修を強化することで組織全体のリスク意識が高まりました。
複数部署にまたがる不正構造の可視化と是正
ある流通業の企業では、商品仕入れに関する金額操作の疑いがあり、部門間で責任のなすりつけが発生していました。社内での調査が難航する中、第三者として探偵事務所を活用した結果、仕入れ部門と販売部門の複数の社員が共謀していた事実が判明しました。外部調査により客観的な証拠が収集され、社内対立を抑えつつ適切な処分が可能となりました。また、企業はその後の再発防止策として、部門をまたいだ業務チェック体制を整備し、内部通報制度の運用強化を実施しました。
よくある質問(FAQ)
Q.調査対象に知られずに実施できますか?
A.はい、多くのケースでは調査対象に知られることなく調査が行われます。調査機関は、対象者と直接接触せずに情報収集を行うノウハウを持っており、外部から不審に思われない形で調査を進めることが可能です。特に社内での不正調査では、関係者に気付かれることなく調査を行うことが求められるため、事前に対象の行動パターンや職務内容を把握し、調査の時間帯や方法を綿密に調整します。ただし、違法な方法(盗聴や不法侵入など)は禁止されており、法律の範囲内での対応となりますので、安心してご依頼いただけます。
Q.調査を依頼する際に準備しておくべき情報は?
A.調査をスムーズに進めるためには、対象者の基本情報(氏名、所属部署、勤務時間帯など)のほか、不正の疑いがある具体的な行動、関係者や場所の情報など、可能な範囲で詳細な情報を用意しておくとよいでしょう。また、疑わしい期間や証拠になりそうなデータ(メール、勤怠記録、映像記録など)があれば、それもあらかじめ共有することで、調査の精度が高まります。情報が不足している場合でも、初回相談の中で調査機関がヒアリングを行い、必要事項を整理してもらえるので、初めてでも安心です。
Q.調査結果はどのように提供されますか?
A.調査結果は、通常「調査報告書」という形式で文書化されて提供されます。この報告書には、調査の目的、実施内容、発見された事実や証拠、調査日時、場所などが時系列で記載されており、写真や図表を用いた視覚的な資料も添付される場合があります。企業が懲戒処分や訴訟対応を行う際の重要な資料となるため、報告書の内容は法的効力を持たせることを前提に作成されます。また、必要に応じて報告書の内容についての説明や今後の対応策について、アフターフォローとしてのコンサルティングが提供されることもあります。
内部不正を防ぐ組織体制づくりの重要性
内部犯罪は、企業にとって決して他人事ではありません。組織の規模や業種を問わず、横領や情報漏洩といったリスクは常に存在し、それらは企業の資産と信用に直接的な打撃を与える要因となります。対策の第一歩は、不正を「起こさせない」「見逃さない」組織風土を育てることです。そのためには、内部統制の強化、透明性のある業務プロセス、従業員の倫理教育など、日頃からの仕組みづくりが欠かせません。また、兆候が見られた際には迅速かつ適切に対応できる体制を整えておく必要があります。さらに、調査の専門家を適切に活用することで、自社では把握しきれない事実を客観的に明らかにすることができます。内部調査に限界を感じたときや、法的に確実な対応が求められる場面では、迷わずプロの力を借りる判断が重要です。調査結果はその場限りで終わらせるのではなく、再発防止策や組織改革の指針として活用することで、より健全で信頼性の高い企業運営が実現します。経営陣が率先してリスク対策に取り組むことが、社員の安心感と企業の長期的な発展につながります。今こそ、内部犯罪対策を企業の経営戦略の一環として位置づけ、行動に移していくことが求められています。
※当サイトでご紹介している相談内容はすべて、探偵業法第十条に準じて、個人情報の保護に十分配慮し、一部内容を変更・修正のうえ掲載しています。法人企業向けガイドは、企業活動におけるリスク対策や内部調査、信用調査など、法人が探偵を活用する際に必要な情報を分かりやすく整理・提供するコンテンツです。安心・合法な調査の進め方をサポートします。
週刊文春に掲載 2025年6月5日号
探偵法人調査士会が運営する「シニアケア探偵」が週刊文春に掲載されました。一人暮らしの高齢者が増加している背景より、高齢者の見守りツールやサービスは注目されています。シニアケア探偵も探偵調査だからこそ行える見守り調査サービスを紹介していただいています。昨今、日本の高齢者問題はますます深刻さを増しています。少子高齢化の進行により、多くのご家庭が介護や見守りの悩み、相続の不安、悪質な詐欺や被害などの金銭トラブルに直面しています。「シニアケア探偵」の高齢者問題サポートは、こうした問題に立ち向かい、高齢者の皆様とご家族をサポートするために設立されました。

この記事の作成者
探偵調査員:北野
この記事は、はじめて探偵を利用される方や困りごとを解決するために探偵利用を考えている方に向けて、探偵の使い方をできるだけ分かりやすく知っていただくために調査員の目線で作成しました。探偵利用時に困っていることや、不安に感じていることがあれば、当相談室へお気軽にご相談ください。どんな小さなことでも、お力になれれば幸いです。

この記事の監修者
XP法律事務所:今井弁護士
この記事の内容は、法的な観点からも十分に考慮し、適切なアドバイスを提供できるよう監修しております。特に初めて探偵を利用される方は、有益な利用ができるようにしっかりと情報を確認しましょう。法的に守られるべき権利を持つ皆様が、安心して生活できるよう、法の専門家としてサポートいたします。

この記事の監修者
心理カウンセラー:大久保
人生の中で探偵を利用することは数回もないかと思います。そのため、探偵をいざ利用しようにも分からないことだらけで不安に感じる方も多いでしょう。また、探偵調査によって事実が発覚しても、それだけでは心の問題を解決できないこともあります。カウンセラーの立場から少しでも皆様の心の負担を軽くし、前向きな気持ちで生活を送っていただけるように、内容を監修しました。あなたの気持ちを理解し、寄り添うことを大切にしています。困ったことがあれば、どうか一人で悩まず、私たちにご相談ください。心のケアも、私たちの大切な役割です。
24時間365日ご相談受付中

探偵依頼に関する相談は、24時間いつでもご利用頂けます。はじめてサービスを利用される方、依頼料に不安がある方、依頼を受けてもらえるのか疑問がある方、まずはご相談ください。専門家があなたに合った問題解決方法をお教えします。
探偵依頼に関するご相談、探偵ガイドに関するご質問は24時間いつでも専門家がお応えしております。(全国対応)
探偵依頼に関するご相談はLINEからも受け付けております。メールや電話では聞きづらいこともLINEでお気軽にお問合せいただけます。質問やご相談は内容を確認後、担当者が返答いたします。
探偵依頼に関する詳しいご相談は、ウェブ内各所に設置された無料相談メールフォームをご利用ください。24時間無料で利用でき、費用見積りにも対応しております。
探偵法人調査士会公式LINE
探偵法人調査士会では、LINEからの無料相談も可能です。お仕事の関係や電話の時間がとれない場合など、24時間いつでも相談可能で利便性も高くご利用いただけます。