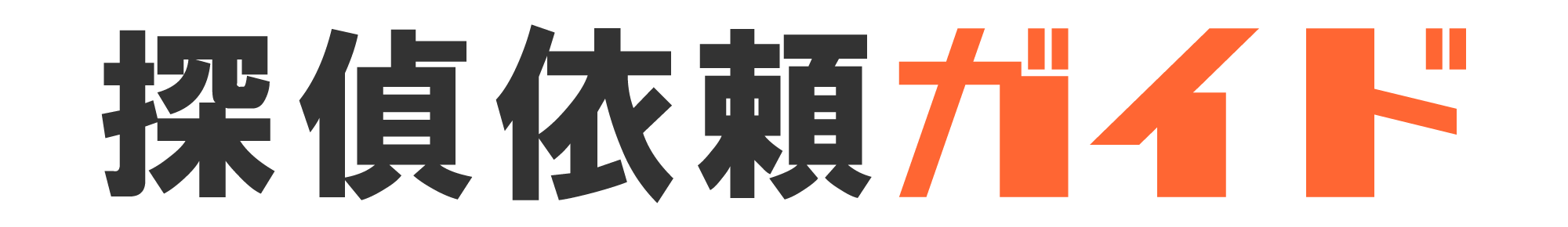外国人労働者の雇用は、今や多くの企業にとって人手不足解消の切り札として欠かせない選択肢です。実際、日本の現場では優秀な外国人材が多く活躍し、企業の成長に貢献しています。しかしその一方で、在留資格の不備、経歴詐称、過去の労務トラブル、文化・言語の摩擦など、外国人雇用には日本人とは異なる特有のリスクが潜んでいるのも事実です。こうしたリスクを見逃したまま採用を進めれば、企業は不法就労助長や行政処分、さらには評判低下といった致命的な問題に直面する可能性があります。採用前に何をどう確認すべきか――その答えは「見える化されたリスク管理」にあります。本記事では、外国人労働者を採用する際に企業が押さえるべき法的・実務的なチェックポイントと、探偵調査を活用した実効性の高いリスク回避手法について、実例を交えながらわかりやすく解説します。
- 在留資格と就労範囲が一致しているか
- 提出された履歴書や経歴に矛盾点がないか
- 過去の雇用トラブルや犯罪歴の有無
- 日本語能力や業務理解度を具体的に測定
- 文化的背景や職場への適応力を事前に評価
増加する外国人労働者と企業の対応力が問われる時代
企業が注目する外国人採用の背景
少子高齢化に伴う人手不足が深刻化するなか、外国人労働者の受け入れは多くの企業にとって重要な選択肢となっています。特に製造業、介護、外食、建設などの現場では、既に外国人が戦力として定着しており、技能実習制度や特定技能制度などの法的枠組みも整備が進んでいます。さらに、海外で高度な専門教育を受けた人材の採用を目指す企業も増加しており、グローバル化への対応という意味でも外国人採用は広がりを見せています。一方で、採用後のコミュニケーション、文化的ギャップ、在留資格の正確な理解といった運用面の課題は依然として多く、採用前のリスクチェックが重要視されるようになってきました。
見落とされがちな「採用リスク」の正体
外国人労働者の採用に際して、企業側が陥りやすいのは「人手が足りないからすぐに雇いたい」という焦りから、必要な確認を怠ってしまうことです。実際には、在留資格と職務内容の整合性を取らなければ不法就労のリスクが生じますし、経歴詐称や学歴偽装といった事例も珍しくありません。さらに、母国でのトラブル歴や日本での過去の就労先での問題など、事前に確認していなかったために採用後に発覚するケースもあります。これらは企業の信用問題にも直結するため、採用前に可能な限りの情報確認を行う体制づくりが不可欠です。
外国人採用における見逃せない具体的リスク
- 在留資格と職務内容が一致していない|不法就労とみなされるリスクがあるため確認が不可欠
- 経歴や学歴の詐称がある可能性がある|応募書類や面接での情報に矛盾がないかの精査が必要
- 過去に重大なトラブル歴がある場合もある|前職での懲戒処分や逮捕歴などの調査が求められる
- 採用後に重大な労務トラブルに発展することがある|文化や価値観の違いから訴訟・告発に至るケースも
- 不適切な採用が企業信用に影響する|行政指導や報道によりレピュテーションリスクが拡大する恐れ
文化・言語の壁が職場環境に及ぼす影響
外国人労働者と日本人スタッフとの間で、言語や文化の違いから誤解や摩擦が生まれるケースは少なくありません。例えば、日本独特の「察する文化」や上下関係の考え方がうまく伝わらず、職場での協調性に影響を及ぼすこともあります。また、指示がうまく伝わらなかったことで業務ミスが発生したり、外国人スタッフが孤立感を感じて離職してしまうこともあります。こうした文化的要因は事前に面談や適性検査である程度把握することが可能ですが、より確実に状況を理解するには、第三者による経歴・性格傾向・過去の行動履歴などを含む外部調査が効果的です。企業にとっては採用リスクを可視化し、職場トラブルを未然に防ぐ重要な一手となります。
採用段階での「法令遵守」がトラブルを未然に防ぐ鍵
就労可能な在留資格かを必ず確認する
外国人労働者を採用する際に最も重要なのは、その人が「本当に就労可能な在留資格を持っているか」を確認することです。たとえば、「留学」や「短期滞在」の在留資格を持つ外国人は、原則としてフルタイムでの就労が認められておらず、仮に雇用した場合、企業側も不法就労助長罪に問われる可能性があります。また、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格であっても、職種が適合していない場合は違法雇用とみなされることがあります。採用時には、在留カードの確認だけでなく、業務内容と資格の整合性について専門機関への確認を行うことが重要です。
身元・経歴の真偽を第三者で確認する意義
履歴書や職務経歴書に記載された学歴・職歴・資格情報などが正しいかどうかは、企業の採用判断に直結する要素です。特に海外からの応募者の場合は、日本側での裏付けが難しく、事実確認を怠ると、後にトラブルに発展する可能性があります。たとえば、実際には勤務経験がない企業名を挙げていたり、語学力や専門スキルを過大にアピールしていたりする例も報告されています。こうしたリスクを防ぐためには、第三者による信用調査や前職の実地確認、関係者ヒアリングといった外部調査が効果的であり、より確実な採用を実現します。
外国人採用時における経歴確認の重要なポイント
- 履歴書の職歴や在籍企業の実在性|記載された企業が存在しない、または勤務実態がなかったというケースを防ぐ
- 語学力やスキルのアピール内容と実力の整合性|実務で必要なレベルに達しているかを第三者評価で把握する
- 過去の勤務態度やトラブル歴の聴取|問題行動や対人トラブルの有無を事前に明確にする
- 学歴証明書や資格の真正性を証明機関で確認|偽造文書や不正取得のリスクを排除するための基本対応
- 本人提供情報と外部情報との矛盾|表面的な面接では分からない情報の裏取りができる
適法な雇用契約と労働条件の提示
外国人を雇用する際には、雇用契約書の作成と労働条件の明示が、日本人と同様に法的義務とされています。特に、言語の壁や文化的な理解の差によって、契約内容の誤解やトラブルが生じるリスクがあるため、母国語または十分に理解できる日本語での説明が求められます。就業時間、給与、休日、有給休暇、退職手続きなどを明記した契約書の提示はもちろん、本人の理解度を確認する面談の実施や、必要に応じた通訳の手配も推奨されます。契約時の曖昧さが後の労務問題を招かないよう、丁寧な対応が企業に求められます。
自社対応でどこまで確認できるかを見極める
面接・書類審査で判断できる範囲
外国人労働者の採用に際して、企業がまず行うのは面接と書類の確認です。ここでは、語学力や人柄、業務適性の初歩的な判断が可能であり、本人の口から背景事情を聞き出す機会として重要です。また、在留カードや資格証明書のコピーをもとに、資格の種別や期限を目視確認することも基本対応となります。ただし、これらの方法だけでは提出された書類が本物かどうか、経歴が事実かどうかを裏付けるには限界があります。特に、本人が流暢な日本語を話す場合や、用意された書類に不備がないように見える場合には、表面的な印象に流されやすくなる傾向があり、慎重な対応が求められます。
研修や試用期間で見えてくる適応力と課題
採用後の試用期間や研修期間は、外国人スタッフの実務適性やチームへの適応力を見極める重要なタイミングです。この期間中に、指示の理解力や協調性、日本の労働慣習への理解度などを観察することができます。また、勤務態度や時間厳守、報連相(報告・連絡・相談)の徹底など、日本特有の職場文化への順応性も確認すべき点です。ただし、問題が明らかになってから対処するのでは遅く、採用前にある程度のリスクを想定したうえでの評価基準が必要です。事前調査によって潜在リスクが明らかになっていれば、この試用期間も確認の場としてより有効に活用できます。
社内調査では把握できない「外部情報」の限界
企業内部での確認手段には限界があります。たとえば、外国での職歴や学歴の裏付けを取るには、海外現地の教育機関や雇用先への照会が必要となりますが、言語・時差・手続きの問題により自社で行うのは現実的ではありません。また、過去に日本国内で別企業とのトラブルがあったかどうか、警察沙汰や訴訟歴があるかといった情報も、企業単独では把握が困難です。このような「見えない情報」こそ、後の大きなトラブルにつながる要因であり、専門家の調査力を活用する意義がある分野といえます。社内確認と外部調査を組み合わせることで、採用の精度は格段に高まります。
見えないリスクにプロの調査力でアプローチする
在留資格・経歴・素行まで網羅する外部調査の強み
探偵など専門調査機関に依頼すれば、企業が独自には確認できない情報まで幅広く収集することが可能です。たとえば、在留カードの真偽確認や、在留資格と業務内容の整合性チェック、さらには国外の学歴や職歴の裏付け取得など、専門知識とネットワークを活用して正確なデータを提供してくれます。また、過去の勤務先での評価やトラブル履歴、居住地域での風評など、素行に関する情報も客観的に収集できる点が大きな特徴です。企業側の判断に必要な確かな材料を揃えることができ、採用の成否に直結する誤判断を防ぐための強力な支援となります。
調査報告を活用した採用判断と契約内容の最適化
外部調査で得られた情報は、採用の可否を決定する材料となるだけでなく、雇用契約の内容や勤務条件の設定にも活かされます。たとえば、日本語能力が限定的と判断された場合には、業務指示の方法を変える、あるいは適切な指導者を配置することができます。また、過去に勤務態度に課題が見られた場合は、最初から試用期間を長めに設定する、定期面談を設けるなど、リスクを前提とした管理体制の整備も可能になります。調査報告をもとにした事実ベースの判断は、後の労務トラブルを避けるだけでなく、合理的かつフェアな採用環境の構築にもつながります。
企業イメージの維持とコンプライアンスの強化
近年は、外国人雇用における不適切な対応がメディアやSNSで拡散されるリスクが高まっており、企業イメージの毀損につながる事例も増えています。こうした中、採用前に適切な調査を行い、コンプライアンスを徹底する姿勢は、取引先や求職者からの信頼獲得にもつながります。特に海外拠点や多国籍人材を抱える企業にとっては、社内統制の一環として、調査の導入が企業全体のガバナンス強化にも資する形となります。採用の瞬間から企業としての責任を果たす準備が整っているかが、今後の企業評価に直結していくのです。
まずは相談が安心の第一歩。導入前に知っておくべき基本情報
ヒアリングで調査の目的と対象を明確化
外国人採用前の調査を検討する際は、まず調査会社への無料相談を通じて、対象者の概要や調査目的を明確にすることがスタート地点となります。たとえば、「過去の職歴に不審点がある」「提出された書類の信頼性を確かめたい」など、企業が抱える具体的な懸念をもとに、調査範囲や方法が提案されます。この段階では、匿名の相談や簡易的なリスク評価も可能な場合が多く、正式な依頼前に方向性を見極めることができます。無理な契約を迫られることはなく、企業側の意思を尊重した丁寧な対応が基本となります。
調査費用の相場とカスタマイズ可能なプラン設計
外国人雇用に関する調査費用は、調査項目・対象国・調査の難易度などによって変動しますが、基本的な経歴確認や在留資格チェックであれば10万〜20万円程度が一般的な相場です。より高度な身元調査や国外の情報収集を伴う場合は、30万〜50万円程度が目安となります。また、調査会社によっては企業の予算に応じた柔軟なプラン設計が可能であり、「最低限の確認だけをしたい」といったニーズにも対応可能です。依頼時には見積書が明示され、調査範囲・費用・納期が明確に提示されるため、安心して導入が進められます。
報告後のアドバイスとアフターサポート
調査終了後には、詳細な報告書が企業側に提出されます。そこには確認された情報やリスクの有無、注意点などが具体的に記載されており、採用判断に直結する材料として活用できます。また、多くの調査会社では、報告書をもとにしたアフターサポートも用意されており、たとえば「採用すべきかどうか迷っている」「この結果を踏まえてどのような契約内容にすべきか」などの相談にも対応可能です。専門家の客観的視点を取り入れることで、より安全で合理的な人材確保が実現します。
探偵法人調査士会公式LINE
探偵依頼ガイドでは、LINEからの無料相談も可能です。お仕事の関係や電話の時間がとれない場合など、24時間いつでも相談可能で利便性も高くご利用いただけます。
採用後のトラブルを防いだ「調査導入の効果」とは
経歴詐称が発覚し、採用直前にリスクを回避できた例
都内のある小売業者では、外国人スタッフの採用面接を経て内定を出す直前、最終確認のために探偵調査を依頼しました。応募者の提出した経歴書に不自然な点があり、確認を進めたところ、過去に日本国内で勤務していた企業名や職務内容が事実と異なることが発覚しました。調査報告書には、在籍期間が虚偽である証言や、職場トラブルによる早期退職の情報が含まれており、結果として企業は内定を見送りました。この事例では、採用前の確認によって経営リスクを回避できた典型的な成功例となりました。
在留資格不適合が判明し、コンプライアンス違反を未然に回避
地方の飲食チェーンでは、外国人スタッフの増員に際し、複数名の採用を進めていました。しかし、雇用予定者の1名について探偵調査を依頼した結果、現在の在留資格ではフルタイム勤務が認められていないことが判明。本人も制度について十分理解しておらず、企業側も確認が不十分なまま採用手続きを進めていたため、もし採用していれば不法就労助長罪に問われかねない状況でした。この調査を通じて企業は採用方法を見直し、行政指導を受ける前に対応を整えることができました。
採用後のミスマッチを防ぎ、定着率向上に貢献
製造業を営む中堅企業では、過去に採用した外国人スタッフが数カ月で離職してしまうことが続いたため、原因究明の一環として探偵調査を導入しました。候補者の過去の職場での評価や性格傾向、業務適性について客観的な情報を得ることで、採用ミスマッチを回避しやすくなり、結果的に新たに採用した人材は長期的に定着。企業側も適切な業務配置と研修体制を整備するきっかけとなりました。単なるリスク回避にとどまらず、人材定着の向上という効果ももたらした事例です。
よくある質問(FAQ)
Q調査は本人に知られずに実施できますか?
A.はい、多くの探偵調査は対象者に知られない「非通知調査」として実施されます。調査員は法令を遵守しながら慎重に動くため、本人に気づかれるリスクは極めて低く、また企業名が表に出ることもありません。特に採用前調査では、応募者の行動履歴や職歴の裏付け、周囲の評判を確認することが多く、情報収集は合法かつプライバシーに配慮した方法で行われます。安心して導入できる体制が整っているため、企業にとっては“調べていること自体”が相手に伝わらない安全な手段として活用されています。
Q.調査対象が海外にいる場合でも依頼は可能ですか?
A.はい、調査会社によっては、海外の現地ネットワークを活用して海外在住者に関する調査にも対応しています。たとえば、現地での学歴や職歴の真偽確認、在住歴のチェック、過去の勤務先へのヒアリングなどが可能です。ただし、国や地域によって取得可能な情報や調査方法には制限があるため、相談時に「どの国のどの情報を調べたいか」を明確に伝えることが大切です。必要に応じて、通訳や海外パートナーと連携して情報収集が行われるため、海外候補者の採用リスクも正確に把握できます。
Q.どのような場面で調査導入を検討すべきですか?
A.調査導入を検討すべきタイミングは、主に次のような場面です。「提出書類に不自然な点がある」「面接内容と経歴が一致しない」「前職の実態が把握できない」「在留資格に不安がある」「過去にトラブル歴がある可能性がある」このような場合は、外部調査によってリスクの有無を可視化することが有効です。また、重要ポジションや長期雇用を前提とした採用では、より高い精度の情報確認が求められるため、事前の調査を通じて判断材料を増やすことが推奨されます。小さな違和感を放置せず、早めの対応が採用成功の鍵となります。
リスクを見逃さない姿勢が「健全な雇用」を生み出す
外国人労働者の雇用は、企業にとって重要な戦力確保の手段である一方で、法的・文化的な課題が複雑に絡む領域でもあります。在留資格の確認ミスや経歴詐称、文化的摩擦など、採用時の小さな見落としが、大きなトラブルや損失につながる可能性があります。だからこそ、採用前の段階でリスクを見極め、事実に基づいた判断を下すことが、健全な雇用関係を築く第一歩となります。専門調査を活用すれば、企業単独では得られない情報を入手でき、採用精度の向上とトラブルの未然防止を両立できます。今後、外国人材の受け入れがますます進む中で、企業として求められるのは「採用の質」です。その質を高めるために、調査という選択肢を戦略の一部として位置づけることが、持続的な企業成長につながるのです。
週刊文春に掲載 2025年6月5日号
探偵法人調査士会が運営する「シニアケア探偵」が週刊文春に掲載されました。一人暮らしの高齢者が増加している背景より、高齢者の見守りツールやサービスは注目されています。シニアケア探偵も探偵調査だからこそ行える見守り調査サービスを紹介していただいています。昨今、日本の高齢者問題はますます深刻さを増しています。少子高齢化の進行により、多くのご家庭が介護や見守りの悩み、相続の不安、悪質な詐欺や被害などの金銭トラブルに直面しています。「シニアケア探偵」の高齢者問題サポートは、こうした問題に立ち向かい、高齢者の皆様とご家族をサポートするために設立されました。

この記事の作成者
探偵調査員:北野
この記事は、はじめて探偵を利用される方や困りごとを解決するために探偵利用を考えている方に向けて、探偵の使い方をできるだけ分かりやすく知っていただくために調査員の目線で作成しました。探偵利用時に困っていることや、不安に感じていることがあれば、当相談室へお気軽にご相談ください。どんな小さなことでも、お力になれれば幸いです。

この記事の監修者
XP法律事務所:今井弁護士
この記事の内容は、法的な観点からも十分に考慮し、適切なアドバイスを提供できるよう監修しております。特に初めて探偵を利用される方は、有益な利用ができるようにしっかりと情報を確認しましょう。法的に守られるべき権利を持つ皆様が、安心して生活できるよう、法の専門家としてサポートいたします。

この記事の監修者
心理カウンセラー:大久保
人生の中で探偵を利用することは数回もないかと思います。そのため、探偵をいざ利用しようにも分からないことだらけで不安に感じる方も多いでしょう。また、探偵調査によって事実が発覚しても、それだけでは心の問題を解決できないこともあります。カウンセラーの立場から少しでも皆様の心の負担を軽くし、前向きな気持ちで生活を送っていただけるように、内容を監修しました。あなたの気持ちを理解し、寄り添うことを大切にしています。困ったことがあれば、どうか一人で悩まず、私たちにご相談ください。心のケアも、私たちの大切な役割です。
24時間365日ご相談受付中

探偵依頼に関する相談は、24時間いつでもご利用頂けます。はじめてサービスを利用される方、依頼料に不安がある方、依頼を受けてもらえるのか疑問がある方、まずはご相談ください。専門家があなたに合った問題解決方法をお教えします。
探偵依頼に関するご相談、探偵ガイドに関するご質問は24時間いつでも専門家がお応えしております。(全国対応)
探偵依頼に関するご相談はLINEからも受け付けております。メールや電話では聞きづらいこともLINEでお気軽にお問合せいただけます。質問やご相談は内容を確認後、担当者が返答いたします。
探偵依頼に関する詳しいご相談は、ウェブ内各所に設置された無料相談メールフォームをご利用ください。24時間無料で利用でき、費用見積りにも対応しております。
探偵法人調査士会公式LINE
探偵法人調査士会では、LINEからの無料相談も可能です。お仕事の関係や電話の時間がとれない場合など、24時間いつでも相談可能で利便性も高くご利用いただけます。